
料理人
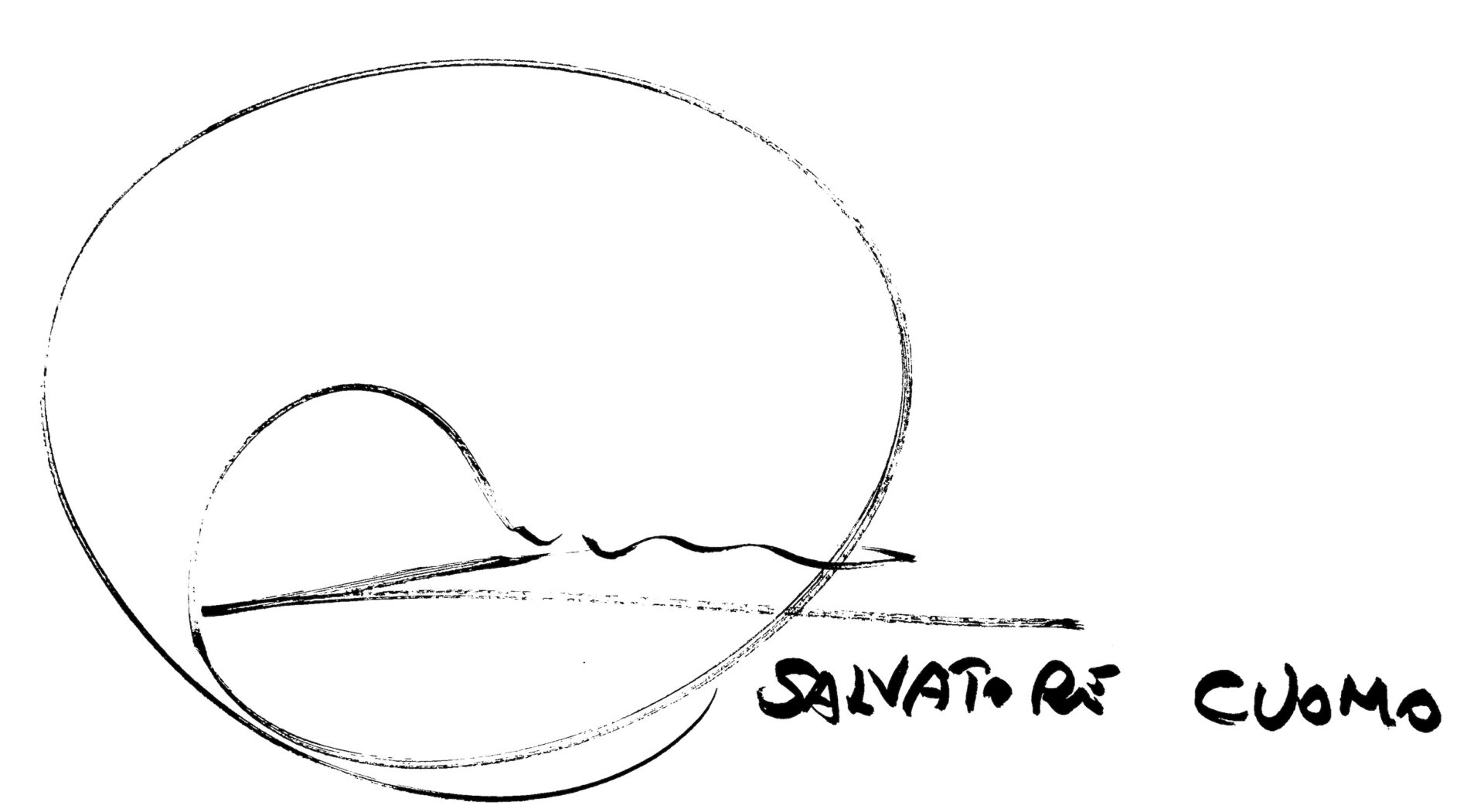
○日田市 在住 ○イタリア ナポリ出身
○52歳 ○株式会社サルバトーレクオモインターナショナル 会長
ナポリピッツァにこだわり、
国内外で250店舗以上を手がける
シェフになるまで
「日本人の母とイタリア人の父の間に産まれ、幼少期はナポリで過ごしました。おばあちゃんっ子で毎日一緒に寝ていました。
日曜日になると30人近くが集まってお昼を食べるので、おばあちゃんはその準備を朝の4時からしていて私も一緒にキッチンに行く。
それが最初のキッチンの思い出です。
13歳の時に父が日本でナポリ料理の店を始めるのを機に、家族で日本に来ました。
千葉の中学校へ通ったのですが言葉の壁が辛く、私は15歳の時に弟とイタリアへ帰りました。
ホテルで働いたり、ピザを専門的に習ったのもその時期です。
18歳の時に父が病気で亡くなりました。
イタリアに墓は作らないと言われていたので父を残して帰るわけにも行かず、二人の弟たちと日本で飲食サービスのノウハウを習得し5年後一緒にお店をやろうと目標を立て、それぞれ飲食やホテル業界で働きました。
私は父の借金もあり、皿洗いなど24時間働きづめでした。23歳の時、イタリア語学校で料理を教えていた時のアシスタントの父親の後押しで、正直怖かったけど、弟たちと3人で父親がこだわったナポリの味を提供するお店『サルバトーレ』を東京中目黒にオープン。
アメリカやローマの薄いピザが人気だった時代に厚手のピザは受けないよと言われたこともあったけど、自信を持っていたし、味だけではなくスタッフの髪型からお店の雰囲気までゴッドファーザー顔負けの『イタリア』の演出によりお客様にその経験をしてもらうことでも人気を得ました。
お店の人気により、僕はプロダクションに入り、テレビのレギュラー番組を何本も抱えるほどでした。
お店に行けないほど多忙となり、結局は体を壊しイタリアへ帰ることに…もう料理はしないと思った時期もありましたが、バイト時代からお世話になっていた日本の父とも呼べる方がイタリアまで来て、自身の会社を一緒に上場させたいと言ったのです。
まだ2店舗しかないのに…と思ったと同時に、やってやろうという気持ちにもなりました。
日本に帰って5年で50店舗まで広げ、上場まですることが出来ました。
その間の僕の大きな変化は、僕にとっての仕事がいつのまにか趣味になっていたということです。」

美味しい果物を求めて日田に移住
地域との関わりを大切に、
フードロス問題にも取り組む
「東南アジアをベースに海外展開を進めてマニラにいた時、コロナのパンデミックが始まり家族と福岡へ。
多くの時間がある中で、料理人として日々アップデートしていきたい!今こそ大事にしているピザの魂となるもの、ピザに必要不可欠なイースト菌を作りたいと思いました。温泉が好きで、福岡から家族で日田を通って黒川温泉へ通っていました。
その時に日田のフルーツと出会い、畑付きの家を見つけて移住することを決め、今はフランスとの2拠点生活。始めはビジネスをやろうなんてこれっぽっちも思っていなかったんです。
フルーツから出来る自然のイースト菌の研究をすると同時に農家さんが市場に出せない規格外のフルーツを大量に破棄していることを知り、フードロスの問題にも取り組みました。
当時のうめひびきの社長さんのお声がけで、水辺の郷おおやまに日田やうきはの規格外のフルーツを使用したジェラート店をオープン。年齢性別問わずに食べていただけるし、果物のクオリティの高さを全国そして海外にも伝えられます。そうなってくるとスイッチ入っちゃって(笑)。
フードロス問題と共に聞こえてくるのは地方の人材不足。高齢化を嘆くのではなく、その地域にあった働き方を考える必要がある。
私は冷凍ピッツァを作りました。シェフである以上味や食材のこだわりはあります。でもテクノロジーの進化も受け入れていきたい。
10年前の自分だったら考えもしなかった冷凍ピッツァ。技術の進化と出会い、冷凍のナポリピッツァをこの大山で地元の女性たちと作っています。
日々研究は続けていますが、今すでにこの大山とパトリア日田2階のカフェ、そして東京ではJR九州系列のホテルでの販売。
東京でのパーティーでも提供し、粉や食材のこだわりを説明した上で食べていただき、最後に冷凍であることを話すとみなさん驚いていました。
仕事は楽しくないと意味がない。休暇を取らなくても、それが趣味のようになれば毎日が休みのようなもの(笑)。
お金で買えない私たちみんなが平等に持っている『時間』を大切にしたい。若い方にも自分の好きな仕事を見つけて欲しいです。
仕事が自分にとって意味のあるものにして欲しい。義務ではなく学びや体験と刺激になるもの。
私は30年間飲食のど真ん中でやってきて、今その時間をここ日田で過ごしている。意味があるんだろうね、私にとって、この日田は。」
Vol.079 UNDER THE SAME SKY
Photo by Cotaro Ishii
Text by Yu Anai


