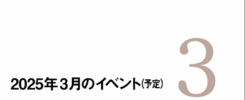誰かと仕事のことを話していて、噛み合っていないなぁと思うことが、ある。後々考えてみると「仕事」という言葉の意味が互いに違っていたのでは?と気付く。そもそも定義が違うのだから、話が噛み合うはずはない。「仕事」ってなんだろう。
辞書を引いてみた。
①何かを作り出す、または 成し遂げるための行動
②生計を立てる手段として 従事する事柄。職業。
③したことや、行動の結果。業績 と、記してある。
他の辞書を見ても順序は変わらない。そうか、ぼくは「仕事」を①として話していて、相手は②として話しているから噛み合わないのだ。まずは互いに定義を揃えるところから始めないと、見当違いなまま話が進んでしまうということだ。 おもしろくなって、よく学校に通えていないこどもたちも来てくれるから、学校や教育のそもそもは?と調べてみる。学校の語源はギリシャ語のスコーレ(スコレー)。日本語で「閑暇」。要するに「暇(ひま)」だ。笑っちゃったけれど、実は、ここでは単なる暇(ひま)ではなく『学問や芸術に専念し、幸福を実現するための自由で満ち足りた時間』と書いてあった。果たして今の学校って、そんな場所になっているのだろうか?と現場に興味が湧いた。
また「教育」の語源は、ラテン語の「引き出す」(エデューケレ)と「養い育てる」(エデュカーレ)を合わせて命名され、〝ひとりひとりの子どもが持っている資質や才能を引き出し、それらを伸ばし発達させ、健やかで心豊かな実りの多い人生を送ることができるように育ててゆく営み〟と記してある。もし、現場の全員がそこに向かう為に集まっている場所になっているなら、きっと行きたい場所になっているはずだよな、とも思えた。
やはりまず、お互いに定義を揃えることから始めよう。たとえ最初は面倒臭がられたとしても、後で話が違うってなるよりずっといい。そして、迷った時にはみんなで「そもそも」に立ち返ってみるのがいいのかもしれない。気付けば、春の足音がもうそこまで来ている。