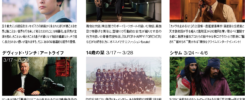「大鶴のパワースポット」
今回は、大鶴町のパワースポットを紹介します。大鶴は相撲の神様の日田殿や井上準之助を代表する地域ですが、縄文や弥生や中世において重要な地域だったのです。そこには、英彦山との深い縁がありました。大鶴に在住の江田さんからその、「気」を言葉にして頂きました。動画でも紹介しています。ぜひご覧ください!
JR廃線となった旧大鶴駅舎。今は短くなったホームに立つと、目前に手に届きそうな山々に囲まれた美しい平野が広がり、春は桜、田植えの後は、くっきりと木々が映る水面鏡、夏は幾重にも折重なる深い緑の景観に、私は日々癒やされている。この自然豊かな大鶴に、はるか縄文時代から人が住んでいた。駅舎から上手に登った鶴河内町下河内地区の鶴河内川沿いに、縄文前期(約六千年前)の集石炉と呼ばれる調理場の跡や、木の実を貯蔵していた穴が。また福岡県境の大肥町吉竹地区では、縄文中期(約五千年前)の船元式土器が発見されている。非常に不思議に思うのは、『比多考古』の資料によると約六千三百年前の鹿児島県鬼界ヶ島のカルデラ大噴火により、九州の縄文人は全体の9%となり、ほとんど人が住める状況ではなかったそうだ。なのに、なぜこの大鶴に生活の痕跡があったのか。
また駅舎の下手に広がる大肥川沿いの平野には、弥生時代前期の集落の遺跡が発見されている。百件以上の住居の周囲に溝を張り巡らせて農耕や木の実を加工し、首長は木製の鎧を着て、祭祀を執り行っていた。地理風水を、ご研究されている禅月庵の別府武志先生によると、英彦山を北側にし、東西の山に囲まれ水の集まるこの大鶴は、英彦山の生きとし生けるものを育む気流を一身に受けている地域だそうだ。現代に住む私自身も癒やされている。この地域特有のエネルギーを古来の人々は感じ取り、守り続けてきたのかもしれない。